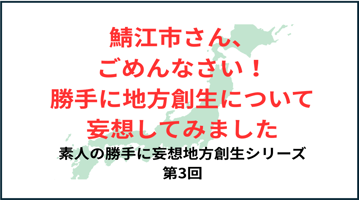◆なぜ、今「人文地理学」が地方創生に必要か...
地域マーケティングについて考える
◆現在の「地域」について考えてみる
『地域のマーケティング』は、なぜ失敗するのか? その答えは、私たちがどの『単位』で地域を見ているかにあります。前回の人文地理学の視点をさらに深掘りし、競争ではなく共存で地方を成功に導くための『経済地理学的アプローチ』を考えます。
まず初めに、改めて「地域」といってもどの単位で定義するかによって見方が変わるのだろうなと思いました。
広い単位で見れば、世界的には「アジア」や「アメリカ大陸」、「ヨーロッパ」等の地域があります。日本人はアジアに属しますが、つまりはアジアの中にも、日本や他の国々があり、国という地域毎での細分化ができます
その日本には47都道府県があり、テレビや動画でも、この括りで様々な企画や議論が行われるので、この単位は地域と言えるのでしょう。また、その都道府県の中には市区町村があり、市区町村ごとにそれぞれの特色があります。「〇〇市へようこそ」といった看板も多数あることから、市区町村単位でのマーケティング活動も多く行われていると言えるでしょう。
住民税は市区町村ごとの単位で設けられており、近年話題になっているふるさと納税はこの単位で行われているため、その観点で考えていくと、公共インフラはこの単位で考えていくものが多くあります。
さらに、それらの市区町村にはいくつかの街で成り立つこともあります。有名な商店街や、名物品となると街単位で取り上げられるものとなります。旅行に行く際にも、特定の街を訪れることが多く、旅行者にとっては周辺情報が重要と言えるでしょう。
また、街や商店街単位で支え合っていることはたくさんあります。むしろ都心まで時間や労力がかかる場所であればあるほど、多くの経済がその街の中で回っているということもあるかもしれません。
このように「地域」もたくさんのくくりに分けられるということが言えるので、地域マーケティングをおこなる場合は、まずはじめに、誰に、何を、どうやって、打ち出すか、そして、なぜ打ち出すか、によってどの単位で考えなければいけないか変わるということがわかります。

◆「地域」の発展について考える
上記のように、各地域毎のマーケティングを行っていけば、地域が発展するのかを考えてみると、恐らく答えはYesでもあり、Noでもあるのだろうなと思いました。
単純にマーケティングを行い、興味を持った人が来てくれれば地域は発展するのはいうまでもありません。
しかし、上記のように、小さな単位で回っている経済があります。今の多くの地域マーケティングはこのパイを取り合っていると言えると思います。
典型例が東京への一極集中です。東京に人が集まれば東京は発展しますが、その分、他地域は人口・労働力を失い衰退していきます。地方が個別に誘致施策を展開しても、それは東京を含む「全国の限られたパイ」の取り合いに過ぎず、結果的に地域全体が弱体化する可能性すらあります。
もちろん、市区町村単位でのマーケティング自体は重要です。住民税の観点からも人口流入は必須であり、その努力を否定するものではありません。ただし、短期的な誘客だけを目的にすると、持続性の低い施策に陥りがちです。
例えば、
-
ある地域は観光に特化
-
隣接地域は宿泊・飲食に注力
といったように、隣接する地域同士が『競争』ではなく『補完』の関係を築くことです。
一方の地域が観光に特化し、もう一方の地域が宿泊や飲食に特化するといった『地域間ポートフォリオ戦略』こそ、限られたパイを増やすための鍵となるでしょう。
◆これから「地域」の発展
上述の通り、相互補完をしていくことでより強い地域の創生が実現していきます。
そのために、経済地理学的な観点で実施していくことは例えば以下だと考えます。
①地域の現状を考える!
自分の地域は地理学の観点で、どのような特色があるのかを把握が重要です。
例えば、都心部までの距離や人口はもちろん、通勤通学による地域外への移動量や地域内のGDP(GDPとまではいかなくても、どの程度、自分の地域内でお金が回っているかを産業毎や、場所毎にある程度把握すると見えてくるものがあると思います)、一定期間内でSNSで発信される回数やその内容、地域民が周辺地域で補完していること、逆に周りの地域の人たちが自分の地域に補完していること等をみてみると、周りの地域との関係性や高め合えるものが見えてきます。
②やらないを考える!
上記でも触れた、周りの地域に補完していること含め、自分地域では手を出すべきでないことを考えてみることも重要です。
例えば、食べ物が美味しいという強みがある一方で、宿泊施設がない地域があったとします。本来は場所の問題や、周辺施設との兼ね合いで作らないほうがいい宿泊施設を作ってしまうと本末転倒になってしまう可能性があります。
これをもり隣街や周辺地域で補ってもらえるのであれば、winwinの関係を作れるので、自分たちではやらない・やれないこもを考えてみることも重要です。
③補うことを考える!
地理学的に考えてみると、様々な特徴が改めてわかります。
通勤通学で地域外で行く人はどのような交通手段を利用しているのか、その混雑状況はどうか、また、人口に対して地域内で回っているお金が少ない場合は、移動手段の問題がある可能性があるかもしれません。
電車や新幹線のように開発にコストがかかってしまうものはすぐに実現が難しくても、バスの本数の改善や最近話題のレンタル自転車があることによって、地域住民や旅行者にとって大きなメリットになる可能性もあります。
④地域資源を活かした連携型プロジェクトを考える!
自地域単独での取り組みではなく、周辺地域と協力したプロジェクトを企画・実施に向けて、自分の地域からさらにもう一つ大きな地理単位での取り組みを考えてみると良いでしょう。
-
地域の文化や特産品、観光資源を活かした共同イベント
-
産業や教育、観光などの分野での地域間協働プログラム
-
複数地域を回遊するスタンプラリーや体験型観光の連携
地域単独では集客が難しい場合でも、周辺地域との協力で付加価値を生み、相互送客や経済波及を狙える。
ここまで出したものは一例ですが、このように、自分たちの地域の特性を活かし、さらには周辺地域の特性を生かすことで更なる地方創生につながるのではないかと思います。
この記事が地理を改めて経済的に考えるきっかけになれば幸いです。